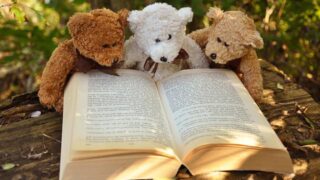訪問看護ステーションに転職し、1年が経ちました。
それまでずっと病院勤務だったので、同じ看護職とはいえ、仕事内容も考え方も働き方も全然違っていて。
それまでの“病院で管理する”という考え方を“その人の生活”にシフトさせながら、少しずつ訪問看護師/助産師になってきたと思っています。

そして、手探りで始めた母子訪問看護。
転職したときは、今の訪問看護ステーション内で母子訪問看護が立ち上がったばかりであり、「〇〇県 母子訪問看護」で検索しても何も表示されない状況から1年。
今では利用者さんが増え、スタッフも増員し、支援してくれる医師も増えました。
「〇〇県 母子訪問看護」で検索するとすぐにヒットし、毎月問い合わせが来るようになり、母子訪問看護自体も知られるようになったなと感じています。
母子訪問看護を始めて1年。
これまで10年以上病院勤務をしてきた私が、訪問看護ステーションに転職し、母子訪問看護を1年してきて感じたこと全てを、お話しいたします。
母子訪問看護が広まり、助産師の働き方が増えますように。
育児を頑張るママ達の支えがもっと増えますように。
助産師こぐまが母子訪問看護を始めたきっかけ
私が母子訪問看護を始めたきっかけについては、こちら→『助産師こぐまが、母子特化型訪問看護を目指したきっかけをお話しします。』をご覧ください
一部引用すると、
もともと訪問看護には好印象を持っていて、看護師としての技術もある。
これまでのキャリアを通して、いくつかの産院と細いながらもすでにつながりがある。
周産期メンタルヘルスケアについては、対応に悩みながらも、たくさん勉強してきた。
私自身が産後うつになりかけて、私自身が地域保健師や精神科に助けられた。私だから出来る、この地域の母子訪問看護の“一歩”を作れるのではないか―
という傲慢な思いからです!
傲慢ですが、ひしひしと、すごく燃えていました。
途中揺らぐことはありましたが、現在も燃えています。
この1年で学んだこと、挫折したこと、嬉しかったこと、感じたこと
初めての訪問看護に緊張し、初めての母子訪問看護を模索する日々
訪問看護ステーションに転職したばかりの頃は、母子訪問看護は1件もありませんでした。
全て看護師としての訪問看護であり、HOTや褥瘡、認知症など、様々な疾患、状態の利用者さんのところへ訪問していました。
初めて聞く疾患も多く、訪問前に一通り調べて訪問同行し、先輩スタッフから毎日毎日勉強していました。
利用者さんも優しく、訪問初心者なのに先輩同様一人前として接してくれます。
それが資格の重さだな、とも感じました。
知らない疾患、馴染みのない診療科、初めての訪問であっても、「看護師さんが来てくれたよ。」と出迎えてくれる。その嬉しさと、重圧。
「看護師さん、よく来てくれたね。今日もよろしくね。」と言ってくれる思いに堂々と応えられる看護師になろうと、毎日背筋を伸ばしていたと思います。

訪問看護独特の制度の使い方、違い等は、人によって教える内容が微妙に違っていたり、部分的な内容で全体像がわからなかったので、その年から始まった「在宅看護指導士」の勉強をし、資格を取得しました。
そのときの記事はこちら→『助産師こそ在宅看護指導士を勉強すべき。母子訪問看護を広げるために、理解し協働していく。』です。
母子訪問看護の初依頼は、忘れもしない5月のGW前でした。
管理者と一緒にウキウキした気持ちで訪問に行ったのを覚えています。
ママの頑張りを労り、授乳やミルクの指導、沐浴を行い、育児の相談にのったり、世間話などでママの気分転換を図る。
助産師としてこれまで当たり前に行ってきたことを、行う場所を病院→自宅に変えただけであり、これでお金をもらっていいのかな?なんてよく話をしていました。
話をするたびに、訪問看護はそもそも病院で行ってきた看護を自宅で提供するというスタイルであり、これでいいんだ、という結論に落ち着いていたと思います。(今もこの考えをベースにしながら、より多面的にケアができるようになってきたと思います)

あとは、訪問看護の制度を母子訪問看護に当てはめたらどうなるのか、具体的には医療保険利用のため訪問時間と回数はどうするか、どんな訪問パターンだと利用者のためになるだろうか、こども医療費助成を使った請求書の見方など、調べては話し合い、調べては教え合いながらやってきました。
後日管理者から「母子の最初っからこぐまさんは頑張ってくれたと思ってる。」と言われ、ひそかに嬉しかったのを思い出します。
あの時も今も、わからないことを調べ、それを訪問につなげ、それをスタッフ間で確認しながら共有し、次に繋げていく、というのが楽しくて仕方ないです。
母子訪問看護が増えてきて、1人で抱えるプレッシャーが増えてくる
母子訪問看護の依頼が少し増え、3件前後になった頃でしょうか。
それまで助産師のみで訪問に行っていましたが、スケジュール的に看護師と行かないと助産師が回らないという事態になってきました。
看護師も母性看護の勉強、実習を経て看護師となっていますが、確かに母性看護領域に限れば助産師の方が経験があり、母子訪問看護のケアが助産師に一任されることもありました。
指導に関しては私のみが行うという形での訪問が続き、母親(あるいは父親、祖父母)と子どもへのケア全てを自分が背負っているという感覚があり、何となくどんどん窮屈になってきたことを覚えています。

本当は全部背負う必要なんてなくて、わからないことはわからないと言えばいいし、出来ないことは出来ないと言えばいいし、それでも判断できないことはやっぱりわからないと言えばいい。
確かに私がメインとなるかもしれないけど、看護師だって沐浴もできるし、全身状態の観察はできる。肩肘張らず、もっと仲間を信頼していたら良かったな、と今になって思います。
また、1回の訪問で解決できなくていいんです。
病院は解決志向で、訪問看護でも次の訪問まで時間があくなら今解決しないといけない問題も出てくる。でも相談される内容全てが、その日のうちに全部解決しないといけない問題ではないんです。

その見極めは、全く出来ていなかったと思います。
相談されたら何とか答える。10相談されたら10答える。
訪問中の限られた時間で、助産師は私だけ。
―そう切羽詰まってくると、やはり誤った判断や対応をしてしまうこともありました。
誤った指導ほど迷惑をかけるものはありません。未熟だったなと思います。
母子訪問看護を始めて半年。嬉しい出来事と、困難なケースの始まり
手探りで進んできた母子訪問看護。
半年経ってくると、訪問利用者さん達自身の成長もあり、嬉しい出来事が増えてきました。
体重がようやく順調に増えてきた、ママが眠れるようになってきた、ママとの話題が増えてきた、生活のリズムが見えるようになってきた。
一番は、対応の難しかった産後うつの利用者さんから、「こぐまさんの訪問を待ってるね。」と言われたことです。とても淡々とした声色での発言でしたが、この一年で一番嬉しかった出来事で、私の耳にずっっっと残っています。
あの!
ずっと関わってきた方で!
表情暗くて、視線合わなくて、私が行く度に「あ、あなたね…😮💨」って言われてた方から!
『(次の訪問)待ってるね』って!!待ってるね!!って!!!
まだ3ヶ月だけど訪問看護やってて良かったです!!😭#母子訪問看護
— 助産師こぐま🧸 (@koguma_hukugyo) July 25, 2024
そして、私にとって重要な利用者との出会いがありました。
かねてから、周産期メンタルヘルスケアとして妊娠期から関わりたいという私と管理者の思いがあったのですが、なんと妊娠期からの訪問看護でした。
妊娠末期からの介入であったため、保健指導内容等急ピッチで進めたのを覚えています。その方は壮絶な分娩を経て、強い育児困難感等を持って、毎日一生懸命自分と向き合い、今も生活をされています。
妊娠期からの関わりを顧みる機会を持てたこと、疾患や家族理解など、非常に多くのことを学ばせてもらっています。
詳細は書けませんが、学びを一言でいうなら「誠実であれ」です。
“病人”として見るのではなく、相手の人間性、これまで大事にしてきたこと、生活歴など“人となり”を理解し、疾患の勉強はするけど“その人に人として関わると相手も返してくれる”ということ。
当たり前ですよね、訪問看護は生活の中に入るから。病院で病気を見ているわけではないから。
ちなみに、この方は小瀬古さんの言葉を借りると私にとっては「横綱級」のケースでした。
今は「小結級」くらいになっていると思います。
「横綱本」を読み、“精神症状が影響する生活の状態”に注目するようになってから、相手の精神状態にこちらが右往左往しないようになってきたかなと思います。
ただし、他のスタッフはまだこの方を「横綱級」と認識しているようです。
私がそのスタッフに上手く助言が出来ないところを考えると、まだ小瀬古さんの技と型は身についていないと思います。
“横綱級”の方が、だんだん“小結級”くらいにはなってきました😊
それでも三役であることは変わらない💪
相性や体調によっては困難になり、技を間違えるとすくわれる。
8-7か9-6で勝ち越しながら、平幕〜三役級にしていきたい🧸#訪問看護#精神訪問看護— 助産師こぐま🧸 (@koguma_hukugyo) March 28, 2025
始めて9ヶ月にして、助産師人生初めての“クレーム” 反省と、頭を下げる日々
母子訪問看護を始めて約9ヶ月で、私に大きな転機が訪れました。
訪問していた家庭のお子さんに重大な状態変化があったにも関わらず、適切に対応できなかったことで、そのご家庭や病院等の関係各所を巻き込む事態となりました。
連日の話し合い、問い合わせ、ふり返り、日々の訪問に行っている中で、そのご家庭から私個人にクレームが入りました。

「クレーム」と表現していいのか迷いましたが、内容は「ご要望」より強いもので、私自身への戒めを込めた意味で「クレーム」と書いています。
訪問看護を始めてから…というか、おそらく助産師になってから、初めてのクレームでした。
以前から私の言動で引っかかることがあったらしく、前述した「適切に対応できなかったこと」と、それで事態が大きくなったことで、クレームを入れるに至ったようです。
反省点は大いにあるのですが、反省しながらも訪問は続きますし、私がそのご家庭に訪問に行けなくなったことで別のスタッフが訪問に行くことになり、ほとんど休憩なく私の“抜け”を埋めてくれるスタッフに頭が上がらず、何となくぎくしゃくしたような日もあったと思います。
あの時どうしたら良かったのか、それまでの私の言動は何がダメだったのか、毎日毎日考えていました。胃薬を持ち歩いてました。
ここに書ける範囲でふり返ると、ある利用者の方が状態悪化し、医師からの特別指示を受け連日1人で訪問しており、非常にストレスが強かったことが挙げられます。
“もう訪問行きたくないな。何か月訪問してても関係性も作れてなかった。適切に対応できなくてあの子には悪いことをした。あれは、もちろん私が悪いのだけど、私だけなのか?いや、私なんだけど…。もうこんなお荷物いらないんじゃないか。私が辞めて誰か別の人を雇った方がいいと思う。誰か雇ってって言おうかな。”
などなど……まぁ惨めなことばかり考えていました。

余談ですが、後日他のスタッフから「よくあの時辞めなかったね!」と励まされました。
管理者、スタッフ、利用者からの支えを受け、訪問看護を続ける意味を持てた
私がどうして辞めずに続けられたかというと、これもいろいろと理由があります。
まず、他のスタッフがとにかく私の“抜け”をカバーしてくれたこと。休憩がない日もあり、私に思うところもあったと思いますが、ぎくしゃくはしても、そもそも顔を合わせる時間すらなく、スタッフから私へのネガティブな言葉は聞かれませんでした。
あと、管理者は私の行動や態度などを見て、文字通り叱咤激励をしてくれました。そして、私が抜けても母子訪問が回るよう調整をしてくれ、私を別の訪問に割り当てることで、「私がこの訪問看護ステーションにいる意味」を持たせてくれました。
具体的に言うと、母子訪問看護の一部は行かず、介護や医療など看護師の訪問に行っていました。これが、私にとっても、おそらく訪問看護ステーションにとっても、良い影響を与えたと思います。
まず、「私がこの訪問看護ステーションにいてもいいんだ」ということを、内側(管理者)だけでなく外側(利用者)にも認められた気がしたんです。
入職当初に訪問したところへ訪問すると、「久しぶりねぇ、元気だった?助産師さんの方で頑張ってるんだってねぇ。今日はよく来てくれたね。」という言葉が聞かれました。

「よく来てくれたね。」という言葉が、入職当時は重圧のように感じていましたが、この時は「あぁ、私の訪問を喜んでくれる方がいらっしゃるんだ。ここに来ていいんだ。訪問してて良いんだ。」と胸に沁みて、まるで久しぶりにおばあちゃんちに帰ったかのような温かさで皆さんが迎えてくれたことが、私に小さな喜びを重ねていきました。

久しぶりに、訪問看護が楽しいと感じました。
そして、看護師が行っていた訪問に私が行き、私が行っていた訪問に看護師(+助産師の複数訪問)が行くことが続きました。
そこで起きたことは、助産師と看護師の密な情報共有でした。

私以降に入職した助産師は、看護師経験がなく看護師訪問をしたことがありません。
助産師である私が看護師訪問の利用者の話題をショートカンファレンス等で話すと、以前より助産師の方々が前のめりで聞いてくれている(気がする)。また、他の助産師が看護師に母子訪問看護利用者の説明をし、看護師の方も母子訪問看護利用者の理解が深まる。
その良い動きは、今でもずっと続いています。
看護師訪問体制が安定し、訪問以外の業務見直しができた
その動きが続き、看護師訪問に行ける人(私)が増えたことで、看護師訪問が安定したなと(これも傲慢ですが)思っています。
緊急訪問や、訪問看護の日程変更、急な特別指示、新規の訪問看護にも、無理なく対応できることが増えてきました。
看護師訪問が安定し、母子訪問看護も(休憩が少ないながらも)安定した結果、訪問以外の業務を見直す時間が出てきました。
母子訪問看護メインの助産師は相変わらず時間がなかったのですが、看護師や私がマニュアルを見直したり、棚卸、物品補充をしたり、ケアマネ一覧や主治医一覧など「これがあったらいいなぁ。」という表を作成、修正することで、事務的にも動きやすくなっていきました。母子訪問看護では、担当保健師表、発育発達チェック表などを作成していきました。
これにより、月末の報告書作成や日々の連携がスムーズになってきました。

私個人としては、前述したご家庭からはクレームが来たものの、その他の母子訪問看護には行っていました。これまで行けていなかった家庭や、回数が少なかった家庭への訪問が増え、そこでも「私の訪問を受け入れてくれてありがたい」という気持ちがあり、よりケアの見直しや勉強に力を入れていきました。
様々な良書、研修との出会いで、少しずつ知識と技を身につけていく
母子訪問看護を進めていくにあたり、いくつかの本を読んだり研修を受けています。
「事例でまなぶ 助産師ができる周産期のメンタルヘルスケア」を読み直し、村上寛先生の「さよなら、産後うつ 赤ちゃんを迎える家族のこころのこと」、小瀬古伸幸さんの「精神疾患をもつ人を、病院でない所で支援するときにまず読む本 “横綱級”困難ケースにしないための技と型」(いわゆる『横綱本』)、あとは「MCMC母と子のメンタルヘルスケア研修」を受けています。
『横綱本』は今月『壁本』が出版されたので、これも読んだらアウトプットをしていこうと思っています。
「事例でまなぶ 助産師ができる周産期のメンタルヘルスケア」を読んで
↓
『「事例でまなぶ 助産師ができる周産期のメンタルヘルスケア」をレビューする。』
「さよなら、産後うつ 赤ちゃんを迎える家族のこころのこと」を読んで
↓
『さよなら、産後うつ』
まだ第一章の途中ですが、頷きながら読んでいます📕
「薬を飲んでいるときは状態が整っていて、飲まなくてもいいや、と考えがち(意訳)」
そう!段々アドヒアランスが低下していく。なんて説明したらいいか…と思ってたけど、そう、「薬を飲んでいるから整ってる」んだよな✍️— 助産師こぐま🧸 (@koguma_hukugyo) October 1, 2024
「精神疾患をもつ人を、病院でない所で支援するときにまず読む本 “横綱級”困難ケースにしないための技と型」を読んで
↓
横綱本読み終えました📕
精神訪問看護1年未満の若輩者ですが、簡単に感想を。
✅生活に困っている自覚があっても、精神症状に困っている自覚はほとんどない。
なるほど🤔だから、眠れる環境で眠いなら眠ればいいのに…ということが起こるのかと。精神症状からくる生活の困り事で、困っていたんだと。 https://t.co/xPNpHg3Inx— 助産師こぐま🧸 (@koguma_hukugyo) March 23, 2025
『横綱本』は、精神科訪問看護の関わり方について、「こういう考えのもと、この対応でいく。ここで△△という対応をしたらダメ。」と具体的に書かれており、考え方と対応の仕方を一つずつ学べる本になります。
Xでもポストしましたが、「精神症状ではなく生活の困りごとに焦点を当てる(本人が感じている問題を共有する)」「さらに訪問が必要であれば、時間ではなく回数を増やす」「自己管理をしていくことを支援する。自覚している状態変化と、無意識に行っている対処法を有意識化し、本人とスタッフとで共有する」。
この考え方とやり方を知ったことで、その日の精神状態には右往左往せず、「最近の経過の中で今の精神状態はどうなのか。生活の変化はあったのか、今の表情言動は?」と以前より落ち着いて対処できるようになってきました。
実際に、「私は〇〇のときは、△△をしている」という話を事前にされていた利用者さんが〇〇の状態になったとき、本人は△△という対処法を覚えていなかったけど、私との話の中で思い出し、△△という対処をすることに納得し、対処をされ、状態が改善したというケースがありました。
状態が悪化したママ。
以前安定していたときに、「症状が悪化した時の自覚症状と対処法」を聞いていて、その話題を持ち出してみるが、覚えていないとのこと😟
大丈夫👍私は覚えてる👍
以前ママが言われた対処法を一緒に確認して、納得されたので、その対処法をとってみる。そしてまた来週へ🏠🚗
— 助産師こぐま🧸 (@koguma_hukugyo) February 28, 2025
ベテラン訪問看護師にとっては当たり前の技かもしれませんが、私にとっては小さくとも確実な一歩で、自分の学びが活かせたと感じられた出来事でした。
少しずつ技が身についてきている、そして、これからも少しずつ成長していける、そう思っています。
母子訪問看護に感じる可能性、将来性
母子訪問看護は、まだまだ始まったばかりです。それでも少しずつ広がってきています。
母子訪問看護の“強み”とは?
よく聞かれる「産後ケアと何がちがうの?」という点は、「医師の指示により医療ケアを行っていること」かなと思っています。
行政の補助が出て、“すべてのママが対象”である産後ケアに対し、医師の指示があり“何かしらの診断がついた母子”が対象。子どもの発達や精神症状の変化などを、医師につなげることが出来ると思っています。
「先生がそれでいいよねって言ったから。」と言って、少しずつ状態悪化をしていても次回受診まで受診を待つ方もいます。少しずつ状態悪化していることの自覚がない方もいます。
そこは自宅に訪問して「今の生活」をずっと見ている訪問看護の強み。状態が良くても悪くても寄り添い、「病気があっても生活をする」ことを支えていきます。

ただでさえ不安やわからないことが多い育児。
でも、「そんなに気張らんで、これくらいで大丈夫ですよ」が、病状によっては受け入れられないときもあります。
今の状態で、今の生活にどんな支障が出ているのだろうか、本人がしたい育児を叶えていくにはどういう方法があるのか、子どもの状態は本当に大丈夫か、そんなことをずっと考えて、提案し、また考えています。
精神状態に不調を持つ方は、私が思っていたよりもメンタルが崩れては整い、崩れては整いを繰り返している印象です。「訪問看護が入ったから、落ち着いて育児ができてます!」とは正直言えないです。
それでも、助産師として育児相談にのれること、精神症状や子どもの病状について医療者として関われること、医師や必要時は保健師などと連携してサポートを厚くできることは、きっとママ達の支えになれているのではないかと思っています。
それでも、その人がしたい生活を送るために
また、診断がついた病気の病状とは別に、育児をすることでの“トラウマ”が現れる方もいます。
具体的には、自分はネグレクトをされてたんじゃないか、虐待体験があり子どもを愛されるかわからない、愛せているのかわからない、なんで自分の母親はこんなことしてたんだろう…そういう“トラウマ”が浮かび、それをその言葉のまま訪問看護師にぶつける方もいました。
本人にとってはそこを自分の中で消化しないと、進めないんです。もう過ぎたことで「解決」はできないけど、その“トラウマ”を自覚した以上、一度そこに大きくぶつかります。
生活自体も困難になり、病状の悪化なのか、その人がアイデンティティを再構築している間の不安定さなのか―そこを明確に区別することは出来なくて、訪問看護としては「それでも生活をする」ことを支援していくのですが…そういう事態も起こり得ます。
そういうときに、生活の中で、「今これが出来ていますよ」「今は休んでお話ししましょうか」「“母”としてじゃなくて“あなた”の話を聞きたいです」…と。
そうやって、伴走っていうんでしょうか、その人がどういう状態であってもその人がしたい生活を送ることが出来るように支援したいな、と思っています。
NICU卒業の子ども、家族をサポートする
母子訪問看護では、NICU卒業のお子さんもいらっしゃいます。
NICU卒業後、一般病棟で育児練習をすることもありますがそれも1泊程度で、「これまで病院で看護師さん達に守られてきたこの子を、家で私が見ることができるのだろうか。」と不安を強く持つ方は多いです。
NICUでの治療はもう終わっているけど、外来通院が必要な程度には何かしら症状があるお子さんです。初産婦でも経産婦でも、この不安は大きいはずです。
それでも、この不安は実際生活しないことには解消されていきません。
そこを訪問看護で、例えば退院当日から訪問する。
どこでミルクを飲ませると都合がいい?ここの布団で休むと休みやすいね、こういう症状が出たら病院に相談しよう、薬は飲み忘れしないように初めは一緒に飲ませましょう、私が抱っこしておくから沐浴の準備をしてみましょう、など、自宅だからこそ必要で出来るケアが多いんです。
訪問看護を始めたらやめられない、ということはありません。自宅でお子さんを育てる不安が無くなっていき、何かあっても解決(受診する、どこかに相談するなど)出来るようになれば、訪問看護終了で良いんです。
なので、NICU卒業して退院した後の生活が不安すぎるという時は、一時的な利用で全然構わないので訪問看護を頼ってほしい。もちろん産後ケアと併用しても良いです。
そうすることで、病院→自宅へ、親子の生活がスムーズに移行できるといいなと思っています。

そして、NICUを安心して卒業できていくことで、NICU自体の稼働率が上がり、次にケアが必要な子がNICUで治療を受けられるようになるといいなと思っています。
子どもの療養生活を支える
通院治療となった後も、言葉通り治療は続きます。
治療の副作用は?家での内服は確実にできている?正確に訴えられない子どもの病状…食事、排泄状態は変わらない?その辺りを家族と一緒に確認することが出来ます。
それにより、訪問のときだけでなく、訪問看護師がいないときに何かあっても異常の早期発見ができる、受診にあたり子どもの状態を整理しておくことで医師に必要な情報(治療後に食欲が落ちたこと、内服をかなり嫌がる…など)を伝えることができます。
以前医師より、「この方に訪問看護が入っているかどうか、で考えることも違ってくる」と言われたことがあります。
訪問看護が、より治療効果の高い&子どもや家族に負担の少ない治療方針へ繋がるのではないかと期待しています。
母子訪問看護をして感じる助産師としてのやりがい、幸せ
「助産師としての知識や経験×新たな勉強」の可能性
助産師であればこれまで多くの育児ケースを見てきていると思います。
それは例えば病院で「新生児期」だけであってもです。新生児期の過ごし方について悩んでいる方は多くて、その知識は確実にママ達の力になります。
「妊娠期」のケアが得意であれば、“何か”を抱えている妊婦さんの力になれます。他の誰かが妊娠期のケアを勉強して、“何か”への対応を勉強するよりも、“何か”への対応のみ勉強した助産師の方が早く手を差し伸べることができるかもしれません。
「産褥期」であっても同様です。例えば産後うつの方の乳腺炎や混合栄養の困難感は、精神訪問看護の知識だけでは対応出来ません。精神訪問看護師が産褥期の勉強をするのと同様に、助産師が精神訪問看護を勉強することでも、この症例に対応することが出来ると考えています。
妊娠期であれば産褥期であれ、助産師が勉強して誰かの仕事を奪うのではなくて、その誰かと協働していくことで、より手厚くサポートが出来ると考えています。

「助産師としての知識や経験×新たな勉強」で、母子訪問看護はどんどん広げることが出来ます。
助産師としての知識や経験、得意なことが助産師一人ひとりで違うのは、助産師であれば何となくわかってもらえると思います。
そこに新たな勉強を加えると、できるケアは広がります!それが母子訪問看護かもしれないし、それが地域保健師かもしれないし、保育園看護師かもしれない。その一つとして、母子訪問看護は大いに助産師が活躍できる場所だと思うのです。
助産師が活躍できる場所については、こちら→「分娩以外」で助産師が活躍できる場所、助産師の資格を活かした働き方【21選】
専門職であり、一部ママ友という関わり
あとは、これはあまり強くは言いたくないのですが、自分の育児生活を活かせる場面があります。例えばどこの公園が遊びやすい、あのスーパーは離乳食の品揃えが良い、一時保育の予約タイミングなどなどです。
「自分の子どものときは、これくらい食べてましたよ。」というような、「自分の子どもは~」というのは、専門職である助産師にはあまり好ましくない言葉だと思っています。
我が家には3人子どもがいますが、所詮3例のケースに過ぎません。
なので「自分の子どもは~」じゃなくて、例えば、「ここまでの予防接種が怒涛に感じるからここまで頑張ろう、この日に発表会?じゃあこの時期は外出控えておこう、〇〇県に行くの?じゃああそこのSAがおすすめですよ」など話していますが、それだけでも十分喜ばれます。
ちょっと詳しいママ友みたいな距離感で話せるときがあって、なかなか楽しい時間だったりもします。

楽しくもあり、そこからその人の生活をなんとなく考えたりもして(発表会だとご主人も休めるのかーとか、旅行が好きなんだなーとか)、そこから考えられるケアもあったり(この時期の旅行は頑張り過ぎてそうだから、旅行計画を聞いてみようとか)で、はたから見たら世間話のように見えると思いますが、とても有意義な時間です。
助産師としての経験と、自分の育児生活を基にした引き出しが増えれば増えるほど、そこでのやり取りが増え、それをケアに活かせているようで、楽しいです。
ママ達、子ども達の笑顔が見たくて頑張れる
助産師でなくても、これは多くの人に理解されると思うのですが、「ママ達、子ども達の笑顔が嬉しい」。
この幸せな場面に遭遇することが多いんです。本当に嬉しい。
母子訪問看護は何かしらの診断がついた母or子なので、うつ状態で不眠だったり、愛着形成不良であったり、発達遅延があったり、嚥下困難があったり、生活をしていると悩みが溢れてくる状態です。
それが、眠れるようになったし眠れて日中楽しく過ごす時間が増えた、子どもと公園に行った、子どもの洋服を買いに行けた、寝返りを見た、ミルクの飲む量が増えて体重が増えた。
これがどんなに嬉しいか。
訪問をしていると、その喜びを真っ先に訪問看護師に伝えてくれて、その時のママの嬉しそうな顔がどんなに胸に沁みるか。
「よかったですねぇ。」と言える幸せ。

医療者としてはその時々に一喜一憂する訳にはいかないんですけどね、その後の強い疲労や、ミルクの吐き戻しとか、たくさん考えるんですけど。
それでも、嬉しそうなママに対して「よかったですね。」と言えることが、嬉しくて仕方ないんですね!
なので、その後母子の状態が悪くなったとしても、状態が良くなっていけるように頑張れる、私が。
「ママ達、子ども達の笑顔が嬉しい」から、その笑顔が見たくて「私が頑張れる」という、一種の好循環(笑)

母子の生活を支援できる母子訪問看護、最高じゃないですか?
(母子)訪問看護の働き方、生活リズムや給料などを紹介
ここでは仕事内容ではなく、働き方について書いていこうと思います。病院→訪問看護へ転職し、生活はだいぶ変わったと思います。

今働いている訪問看護ステーションを基にした内容なので、ステーションによっては勤務体制等変わることをご容赦ください。
まず、日勤のみであること!
オンコール当番はあっても夜勤はありません。オンコール当番であっても、緊急電話がなければ夜はぐっすりと眠れます。なので、夜眠って朝起きるという生活ができます。
これは、病院勤務ではほとんどあり得ないことです。
病院勤務で「夜勤なし」で働いていても、いつか夜勤を言われるんじゃないか?早出遅出を言われるんじゃないか?とも思うし、悲しいことに病院勤務は夜勤手当ありきの給料が多いので…、毎週怒涛の5日勤をしていても給料が少ないということがありました。
訪問看護の給料ですが、これは今いる訪問看護ステーションの、数人にぼかして聞いたものではありますが、「病院日勤のみ」よりは多く、「病院夜勤あり」よりは少ないのかな?という印象です。
夜勤手当や夜勤回数によっては、「病院夜勤あり」と同程度の給料のようです。
私自身はパート時給制なので、月によって結構変動があるのですが、私自身も「病院日勤のみ」よりは多く、「病院夜勤あり」よりは少ないかな?と思います。
訪問看護だとオンコール手当があり、これはステーションによって金額がだいぶ違うので、オンコール手当が高く、多く持つのであれば給料は高くなるんだろうな、と思ってます。

また、うちの訪問看護ステーションは基本的に平日のみの訪問で、土日は休みになっています。
例外は多少あって土日訪問することもありますが、それは時間外扱いで給料が多少高くつきます。毎週末に訪問があっても、1人に負担がいかないよう分けているので、基本的にはほぼ毎週末お休みです。(他のステーションでは土日も基本訪問しているところがあると思いますが、振り替えで休みが取れると思います。)
夜勤がなく、週末は基本お休みとなり、子どもと過ごす時間がかなり増えました。
これまで土曜出勤だったのが休みになったので、それだけでも約2倍に増えました。土曜も日曜も休みなので、どちらかに用事をいれてどちらかでだらだらと過ごすことが多く、特に土曜日の朝は子どもと一緒におさるのジョージを見るのが日課です(Eテレ土曜8:35~)。
今後の展望:利用者も働く人も増え、母子訪問看護が当たり前になるように
母子訪問看護の検討が当たり前になるように
まだ母子訪問看護を始めて1年ですが、これまでの知識を活かせて、新たな勉強も楽しく、やりがいも大きい。
失敗したことや挫折したこともありましたが、それでも私はこれからも母子訪問看護を続けていきたいし、どんどん広がってほしいと考えています。
同業他社が増えることでライバルが増えることにはなりますが、そこは敵対せずに「新しく母子訪問看護を切り拓いていく仲間」として切磋琢磨していきたい。
綺麗事とは思いますが、それがママ達(パパ達家族も含む)、子ども達を支えることに繋がると思うんです。

そして、母子以外の訪問看護同様に、「このケース(母子)だったら、ここの母子訪問看護ステーションに依頼しよう」と強みを発揮していけたらいいなと思っています。
どんどん広がることで、ママ達にも医療機関にも認知されて、自宅での生活が難しいケースには訪問看護を利用することが当たり前になってほしい。
産後外来だったり、母乳外来、産後ケア、保健師家庭訪問と思い浮かぶ支援の一つに、当たり前に訪問看護が検討されるようになってほしい。
子どもだと成長によって訪問看護が数ヶ月で終了することもありますが、精神疾患を持つママの家庭にはおそらく数年単位で関わっていくのだと思っています。
それが、良い重圧、プレッシャーでもあり、数年単位で親子の成長を見守っていきたいという願望もあります。
周産期、産科、小児科領域で働きたい人が活躍できるように
この母子訪問看護には、助産師に限らず小児看護師や、子どもが好きな看護師でも訪問に行けます。そう、産科で働きたかったけど、働けなかったという看護師が働ける場所でもあります。

母子訪問看護は、「母性看護」×「小児看護」×「精神看護」×「訪問看護」です。
かつて、私の武器は「母性看護」しかありませんでした。勉強して、まずは1年やってきました。
分娩施設が集約化され、助産師や産科に興味がある看護師が働ける場所が減ってきている今、母子訪問看護はその働く場所となり、それまでの経験や思いを活かせる場所です。
母子訪問看護が広がり、働く人も増えることで、困っているママや子ども達のサポートがどんどん大きくなっていくといいなと思っています。
まとめ:助産師、看護師、ママ達のために 広がれ母子訪問看護!
私、助産師こぐまが、母子訪問看護を1年してきた思いを書いてきました。
母子訪問看護に興味を持ってくださった方、ここまで読んでくださった方、ありがとうございます。
母子訪問看護をもっと知ってほしい、もっと広がってほしい。
ママ達のサポートとして当たり前に存在したい。
サポートの一つとして母子訪問看護を検討してほしいし、検討したときに検討できるだけの訪問看護ステーションがあるように広まってほしい。
働き方や働く場所に悩んでいる助産師さん、潜在助産師さん、産科希望の看護師さん。
きっと母子訪問看護の中に、活躍できる場所があるはずです。母子訪問看護で働くということ、ぜひ検討してほしいなと思っています。
ママ達へ
ここまで読んでくださり、本当にありがとうございます。
今まさに何かしらの支援を必要とされている方かもしれませんし、以前妊娠出産育児等で辛い思いをされた方かもしれませんし、私たち助産師に興味を持って読んでくださった方かもしれません。
私たち…というと主語が大きくなりますが、それでも私、私たち助産師は、ママ達が健やかに子どもと過ごしていけるよう願っています。力になりたいと思っています。
そのやり方は、ある助産師は分娩施設で、ある助産師は行政保健師として、そしてある助産師は訪問看護で、その他いろんな場所で奮闘しています。場所が違って、それで少し立場が違っても、みんなママ達お子さん達を思ってます。
もし妊娠出産育児に不安があったり、悩んでいることがあれば、相談してください。
そして、良ければ、母子訪問看護の利用も検討してみてください(^^)
ママ達のサポートがもっと増えてくるといいなと思っています。
ママ大好き助産師こぐまより